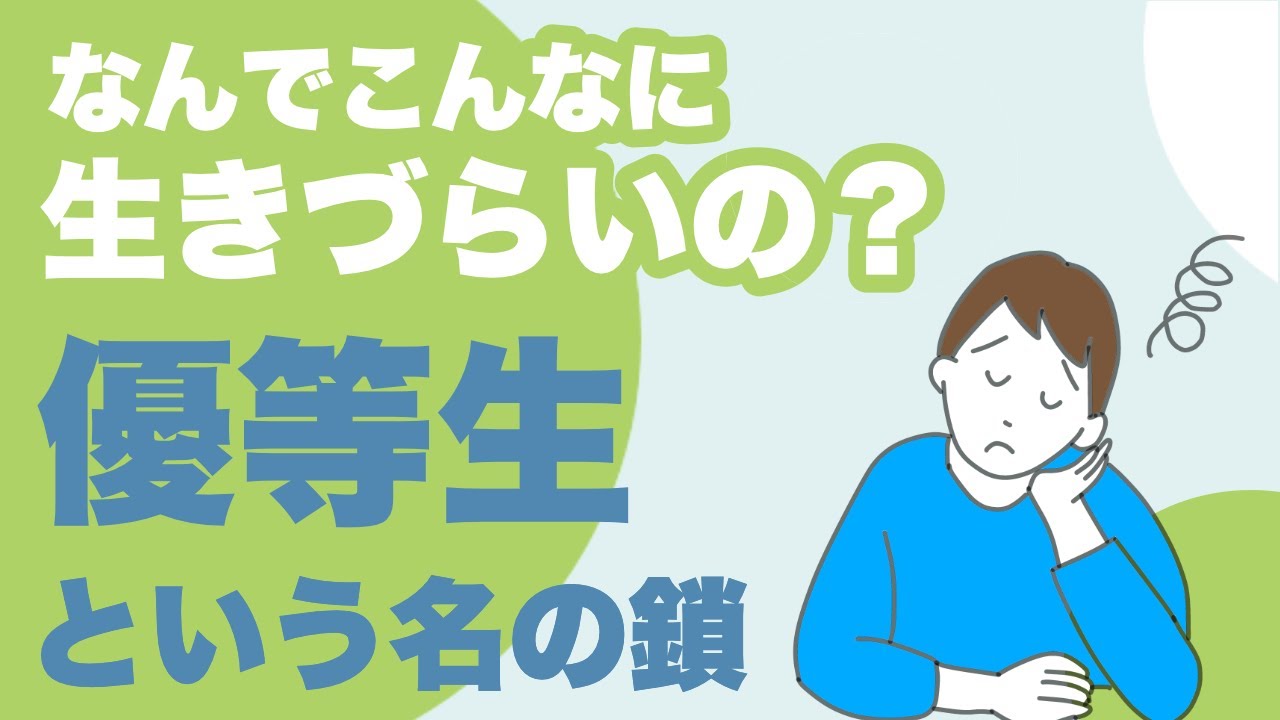生きづらい世の中です。なんとなく苦しいけど、その原因はわからないという人もいます。でも、自分自身に聞いてみると、生きづらさの原因として、自分自身を縛り付けている鎖が見つかるはずです。まずは、その鎖を見つけ出し、ほどいていくと、心も体も軽くなるかもしれません。
「自分はいつも期待されている」と思い込む
優等生と言われる人たちは、先生に褒められるために、ついつい頑張ってしまう性分です。勉強ができる人、学級委員などクラスの世話ができる人、掃除など縁の下で支えている人など、優等生たちは正しい行いで先生や周囲の評価を集めます。でも、いつも優等生でいることはとても疲れることです。一度、優等生と認識されると、優等生であり続けようと頑張るので、その疲れから解放されることがありません。
優等生は、「褒めてもらいたい」と自分で思ってしまうだけではなく、周囲からの「優等生でいてほしい」という期待を受けやすい性分でもあります。先生やクラスメート、家族などから「いい子」であってもらいたいという期待を感じ取って、その期待に沿うような行動を選びがちです。先生やクラスメート、家族が、そのように期待していない時にさえ、「期待しているはずだ」と思い込んで、プレッシャーを自らに課してしまいます。 「誰かに褒めてもらいたい」または「誰かに認められたい」という気持ちのことを承認欲求と言います。誰もが持っている自然な感情ですが、「優等生でありたい」と思ってしまう人にとっては、特に強く、この感情が現れがちです。承認欲求を原動力にして、良い行いをする人もいますが、この感情が強すぎると、自分自身を苦しめてしまうことがあります。
優等生か偽善者か?承認欲求で息が詰まりそう
また、承認欲求が強すぎると、周囲の人にも嫌な思いをさせてしまうことがあります。「自分のことを良く見せたい」という気持ちが強すぎると、「私はこんな良いことをしています」とアピールをしたり、人の目があるところだけを狙って良い行いをしたり、誰の前で良い行いをすると自分に得になるかを計算したりします。こういうタイプの人のことを偽善者と呼ぶこともあり、周囲の人に不快さを感じさせることもあります。
クラスの担任の先生の承認欲求が強すぎる場合、クラス全体が優等生であることを求められるケースもあります。先生が周囲に評価されたいために、生徒一人ひとりが、先生が描く理想のクラス像を強いられてしまいます。先生が周囲に評価されたいという気持ちを持ち、生徒がその先生に評価されたいという気持ちになるので、まさに承認欲求が伝染するように広がり、息苦しさが醸成されていきます。 クラス全員が平等に優等生として扱われるならまだいいのですが、必ず、優等生の中にも順位付けがされていきます。1番の優等生、2番の優等生、3番の優等生、といった具合です。30人学級で、30番目の優等生にとっては、自分が優等生であるとは思えないかもしれません。それでも、いつかは順位を上げたいと、先生の求める生徒になろうと頑張ってしまうのです。優等生の順位を競う状態が続くと、学校生活そのものが、とても息苦しいものになってしまいます。
社会人でも優等生。もはや何がやりたいかわからない!
優等生という鎖は、学校を卒業してもなかなか断ち切ることができません。社会に出てからも、誰かの期待に応えて行動することを続けてしまいます。職場では、上司の期待に応えることを求められるので、優等生的な考え方が、より強くなってしまうこともあります。自分には何が期待されているのかを考えて、それに沿って行動することが、出世する近道だと信じられているので、無理もありません。
優等生という名の鎖に縛られて、生きづらいと感じてしまうのは、なぜでしょうか。それは、自分に期待されていることが、本当は自分が求めていることではなかったり、それどころか、自分はそういうことをしたくないと思っていることを、するように期待されるからかもしれません。
仕事だから仕方がない、社会的に評価されるためにはやむを得ないと考えて、期待されることをやっているうちに、本当は自分が何をやりたいかすら、わからなくなってしまうこともあるでしょう。 また、自分で考えて行動しようとすると、求められていることと自分の考えが違う場合、相手と衝突してしまうので、あえて自分で考えないようにするほうが楽だと思って、思考を止めてしまうこともあるかもしれません。
優劣は誰が決めるのか。気にせずに自分の道を行こう
優等生でありたい人は、褒めてもらいたい人に否定されてしまうと、思考が停止してしまいます。相手が求めることをやったのに、その結果が、相手が求めるものでなかったことで、厳しく叱責されたり、または、責任を追及されることもあります。認められたい人に認められなくなると、モチベーションが著しく低下してしまいがちです。優等生が生きづらいのは、自分自身の考えではなく、褒めてもらいたい人や認めてもらいたい人の考えや都合に振り回されてしまうからなのです。
優等生という名の鎖で生きづらさを感じたなら、一度、優等生をやめてみてはどうでしょうか。優等生をやめるからといって、劣等生になる必要もありません。この優等生や劣等生という言葉は、学校の先生や職場の上司など、管理する立場、評価をする立場にある人から見た「優劣」であり、絶対的な評価ではないのです。
評価されようとするのをやめて、自分で考えて、行動するようにすればよいのです。誰が見ていても、見ていなくても、自分がやるべきと思ったことをやり、それによる周囲の評価も気にしないでいられるなら、心は自由で軽くなれるかもしれません。